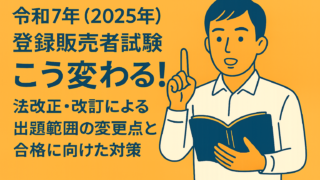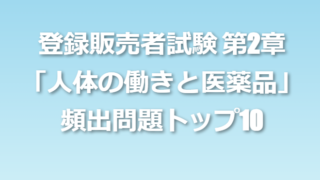登録販売者試験の第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」では、毎年似たテーマの問題が繰り返し出題されています。過去10年分の全国試験を分析したところ、特によく問われる重要ポイントが見えてきました。ここでは頻出度の高い順にランキング形式で紹介し、各項目について受験生が理解しやすいように簡潔に解説します。しっかり押さえておけば、正答率アップにつながるはずです!
1位:薬害の歴史(過去の医薬品被害事件)
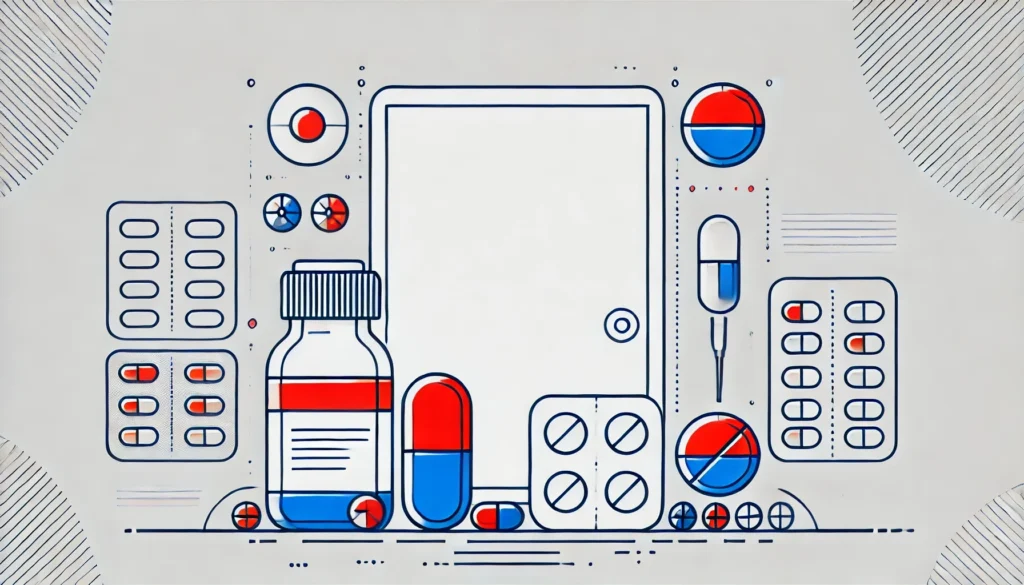
「薬害の歴史」を制する者は第1章を制す! と言われるほど重要なテーマです。過去に日本で起きた重大な医薬品被害の事件は、登録販売者試験でほぼ毎年出題されています。これらの事件を学ぶことは、同じ悲劇を繰り返さないためにも大切です。試験では各事件について、原因となった薬剤や用途、被害内容、社会的対応などが問われます。
代表的な薬害事件の例をいくつか挙げておきましょう:
- サリドマイド訴訟 – 妊婦が服用した睡眠薬サリドマイドにより胎児に四肢欠損などの先天異常が発生しました。この被害への損害賠償を求めた訴訟で、1974年に和解が成立しています。
- スモン訴訟 – 整腸剤キノホルムの副作用によって神経障害(スモン病)が多発した事件です。長期服用による視力障害や手足の麻痺が問題となり、1970年代に集団訴訟が起きました。
- HIV訴訟 – 血友病患者に投与された非加熱血液製剤からHIV感染者が多数発生した事件です。安全性が確認されない製剤の使用が招いた悲劇で、厚生労働省や製薬企業が訴えられました。
- CJD訴訟 – 下垂体性小人症の患者に使用されたヒト乾燥硬膜や成長ホルモン製剤を介して、プリオン病であるクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)に感染した事件です。1990年代に問題化し、国と企業を相手取った訴訟になりました。
- 薬害肝炎訴訟 – 血液製剤フィブリノゲンなどの投与により、多くの患者がC型肝炎ウイルスに感染した事件です。2000年代に訴訟が提起され、国の責任が問われました。
試験対策としては、各事件ごとに「何の薬が原因で」「どんな被害が起き」「どういった経緯で訴訟や制度改善につながったか」を整理して覚えましょう。例えば「サリドマイド事件=睡眠薬で妊婦の胎児に障害」「HIV事件=非加熱製剤で血友病患者がHIV感染」のようにキーワードで結び付けておくと、問題文を読んだときに素早く対応できます。この分野は知識を確実に暗記していれば得点源になります。
2位:プラセボ効果(偽薬効果)
プラセボ効果も第1章で毎年のように問われる定番テーマです。プラセボ効果とは、一言でいうと「薬理作用のない偽物の薬を服用しても、“効く”と信じ込むことで症状が改善してしまう現象」のことです。例えば砂糖の錠剤を「これはよく効く薬です」と言われて飲んだら痛みが和らいだ、というようなケースですね。
試験ではプラセボ効果の定義やメカニズムについて問われます。正答するポイントは、「有効成分がなくても、患者の思い込みや安心感によって実際に体調が良くなる場合がある」という点をしっかり理解しているかどうかです。また、「プラセボ効果は治療効果を高める補助にはなるが、病気そのものを治す力はない」ことも押さえておきましょう。この効果は心理的要因によるものなので、副作用は起きませんが、本物の薬のように病状を根本から改善するわけではありません。選択肢で「有効成分が含まれていないのに治療効果が現れる」といった記述があれば、それがプラセボ効果を説明していると判断できます。逆に「偽薬でも副作用が出ることがある」といった誤った内容に惑わされないよう注意しましょう。
\\おすすめ講座通信講座はこちら//
| 三幸カレッジ | スタディング | SMART合格 | ユーキャン | オンスク.jp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 講座内容 | Web/スマホOK・見放題・テキスト教材あり | Web/スマホOK・見放題・Webテキストあり | Web/スマホOK・見放題・問題演習の解説動画 | Web/スマホOK・見放題・テキスト教材あり | Web/スマホOK・見放題・ダウンロードテ教材 |
| サポート体制 | 質問OK・添削あり・就職支援・ | 質問OK | 質問OK・添削あり | ||
| 受講期間 | 3ヶ月〜1年 | 3〜10ヶ月 | 3ヶ月〜3年 | 3ヶ月〜1年 | 3ヶ月〜1年 |
| 費用 | 35,200円 | 24,800円 | 39,600円 | 49,000円 | 月額1,628円 |
| 合格実績 | 合格率89.0% | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 一般教育訓練 | 対象 | 対象 | |||
| おすすめ度 | ◎◎◎ | ◎◎ | ◎ | ◯ | ○ |
| 公式サイト | 圧倒的合格率89.0%!登録販売者受験対策講座【三幸医療カレッジ】 | スマホで学べる登録販売者資格 | 登録販売者の資格取得なら 「SMART合格対策講座」 | 生涯学習ならユーキャン | 定額で「ウケホーダイ」(登録販売者講座) |
3位:副作用と医薬品の適正使用

医薬品の副作用も頻出項目の一つです。副作用とは、簡単に言えば「お薬を適正な用量で使用したにもかかわらず現れてしまう望ましくない作用」のことです。たとえ正しく飲んでも眠気や胃の不調など軽い副作用が出ることがありますし、時には重篤な症状(例えばアレルギーによるショックや重い皮膚症状など)を引き起こすこともあります。
試験ではまず「医薬品の定義」に関する穴埋めや副作用の意味を問う問題がよく出されます。「本来の目的ではない作用」「有害な作用」といったキーワードで副作用の定義を覚えておきましょう。また、副作用に関連して医薬品の正しい使い方も重要なテーマです。消費者が用法・用量を誤ると副作用のリスクが高まるため、登録販売者としては使用上の注意を守らせる指導が求められます。試験でも「適正使用の観点から正しい説明はどれか」といった問題が出題される傾向があります。
ポイントは、副作用そのものの理解に加え、どうすれば副作用を防げるか(使用のタイミングや併用禁忌の遵守、定められた容量以上飲まない等)を知っていることです。副作用のリスクを最小限にする適正使用を心がけることで、初めて医薬品は安全かつ効果的に使えるという点を試験では問うてきます。このあたりは日常的な常識とも重なる部分なので、具体的な事例をイメージしながら学習すると記憶に残りやすいでしょう。
4位:小児・高齢者・妊産婦への配慮
年齢や状態別の医薬品使用上の配慮も試験で頻繁に取り上げられます。特に小児や高齢者、妊婦・授乳婦といった一般的な成人とは異なる生理特性を持つ人々への注意点は、過去問でも繰り返し問われているポイントです。
- 小児(子ども)への配慮: 子どもの場合、身体が未発達で薬の代謝や排泄機能が十分ではありません。そのため大人と同じ薬でも作用が強く出すぎたり、副作用が起こりやすかったりします。試験では「◯歳未満の乳児にはこの成分を使ってはいけない」といった年齢区分に関する知識や、小児用に用量を調節する必要性などが問われます。例えば「一般に小児とは15歳未満を指す」など基本的な定義も確認しておきましょう。
- 高齢者への配慮: 高齢者は加齢により肝臓・腎臓の機能が低下し、薬が体内に蓄積しやすくなります。また複数の持病で多くの薬を服用しているケースもあり、相互作用にも注意が必要です。試験では「高齢者では一般に若年者よりも少ない用量から開始する」といった記述の正誤を問われたりします。副作用が現れやすいことやのみ込みが悪く錠剤は服用しにくい場合があることなど、現場での配慮事項も含めて理解しておきましょう。
- 妊婦・授乳婦への配慮: 妊娠中の方は胎児への影響を考慮する必要があります。胎盤を通じて胎児に薬が移行し、奇形や発育障害を起こすリスクがあるため、妊婦には原則として不必要な薬は使わないのが鉄則です。特に妊娠初期(胎児の器官形成期)は薬剤の影響を受けやすいので要注意です。また授乳中の方も、薬の成分が母乳中に移行し乳児に影響を与えることがあります。試験では「妊娠〇週目までは薬剤感受性が高い」「授乳婦が薬を飲むときは授乳後すぐ飲み、次の授乳まで間隔を空けると良い」など具体的な対策が問われたりします。
正解のポイントは、それぞれの対象者で「なぜ特別な配慮が必要なのか」を理解していることです。小児は「子どもは単に小さい大人ではない」、高齢者は「体の処理能力が落ちている」、妊産婦は「お腹の赤ちゃんや乳児に影響が及ぶ可能性」といった具合に理由付けして覚えておくと、応用的な問題にも対応しやすくなります。現場をイメージしながら知識を整理しておきましょう。
\\6月13日まで実施中!//
5位:医薬品のリスク評価(用量と反応の関係)
医薬品の効果と危険性を客観的に評価するために欠かせないのが、用量と反応の関係(Dose-Response 関係)に関する知識です。これは「どれくらいの量の薬を使えば効果が現れ、どの量を超えると副作用や毒性が出てくるか」という関係性のことです。試験では、このリスク評価に関する問題が頻出しています。
具体的には、用量反応曲線(グラフ)や専門用語を用いた問題が出されることがあります。例えば「ある薬の作用は一定の用量までは増えるが、それ以上は頭打ちになる(最大効果に達する)」とか、「閾値(しきい値):効果が現れ始める最小の用量」や「LD50:50%の動物を死亡させる用量」「治療指数:薬の安全域を示す指標」といった用語の意味を正しく理解しているかどうかが問われます。
難しく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば大丈夫です。まず用量を増やすと効果も副作用も強くなるが、ある程度で効果は頭打ちになるという基本を理解しましょう。その上で、「少量では効果が出ない閾値がある」「安全に使える上限量がある」「有効な範囲と危険な範囲の差(安全域)は薬によって異なる」といったことを覚えてください。
今述べた基本原理を理解していれば落ち着いて判断できます。難解な計算問題が出るわけではないので、概念をしっかり自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。

6位:一般用医薬品で対処可能な範囲(一般薬の役割)
一般用医薬品(OTC医薬品)の役割についても頻繁に出題されています。これは「医師の処方箋なしで購入できる一般薬が、どんな目的・範囲で使われるものなのか」を問う内容です。国民のセルフメディケーション(自分自身で健康管理すること)を推進するうえで、一般用医薬品にはいくつかの重要な役割が公式に示されています。試験ではその6つの役割すべてを正しく理解しているかがチェックされます。
一般用医薬品の主な6つの役割とは次のとおりです:
- 軽度な疾病に伴う症状の改善 – 日常的に起こる軽い病気や不調(かぜの初期症状や軽い頭痛など)の症状を和らげる。
- 生活習慣病などの症状発現予防 – 高血圧や糖尿病など生活習慣病に関連する症状が現れるのを未然に防ぐ(科学的・合理的なエビデンスがある場合に限る)。
- 生活の質(QOL)の改善・向上 – 病気ではないが体調を整えることで日々の生活の質を高める(疲労回復や栄養補給などを通じて元気を維持すること)。
- 健康状態の自己検査 – 自分の健康状態を自ら確認するのに役立てる(例えば検査薬や体調の変化から健康チェックを行うといった用途)。
- 健康の維持・増進 – 日頃から健康を維持し、更に増進するために用いる(ビタミン剤などで不足しがちな成分を補ったりすることも含む)。
- その他の保健衛生上の役割 – 上記に当てはまらない公衆衛生の目的を果たす(例として、害虫駆除剤や消毒薬なども広い意味で生活衛生を守る一般薬の役割に入る)。
これらをまとめると、「軽い症状の治療から健康維持・増進、さらには予防的な使い方まで、一般用医薬品は幅広く人々の健康に貢献している」ということです。試験では、「次のうち一般用医薬品の役割として誤っているものはどれか」「一般用医薬品で対応できる範囲として正しい記述はどれか」などの形で問われます。公式に定められた6つの項目そのものを覚えておけば、ひっかけ選択肢にも対処可能です。
たとえば選択肢に「重篤な疾病の治療」が含まれていたら、一般用医薬品の範囲を超えているので誤りだと判断できます。また「軽度な症状の改善」や「生活の質の向上」のような記述は正解肢の可能性が高いです。セルフメディケーションの理念をしっかり理解し、「どの程度の症状までなら市販薬で対処してよいのか」「どんな目的で市販薬が活用されるのか」を整理して覚えておきましょう。
7位:医薬品の相互作用(飲み合わせ)
「薬と薬」「薬と食品」「薬とアルコール」など、医薬品を他の成分と併用することで起こる作用の変化が「相互作用」です。試験では併用によるリスクや影響を正しく理解しているかが問われます。
- 相互作用の基本
医薬品を同時に服用すると、お互いの作用が「増強(相乗作用)」「減弱(拮抗作用)」「予測不能な反応」を引き起こすことがあります。相互作用による副作用のリスクが高まる点に注意。 - 代表的な薬物相互作用
- 解熱鎮痛薬(NSAIDs)×抗血栓薬 → 出血リスク増加
- 抗ヒスタミン薬 × アルコール → 中枢神経抑制作用が増強(強い眠気・意識低下)
- 食品との相互作用
- グレープフルーツジュース → 薬の代謝を阻害し、作用が強まる(降圧薬、睡眠薬など)
- アルコール → 肝臓の酵素に影響し、薬の効果が強まる・弱まる場合がある
- 納豆・青汁(ビタミンK豊富) → ワルファリン(血液をサラサラにする薬)の効果を低下させる
試験では、「併用により効果が強まる」「逆に効きにくくなる」「予期せぬ副作用が出る」といったポイントが問われます。「飲み合わせによる作用変化がある」という前提で問題を読み、影響が起こる可能性のある組み合わせを判断しましょう。
8位:医薬品の安定性と保管方法
医薬品は適切な保管が必要であり、温度・湿度・光・空気などの影響で劣化することがあります。試験では、「正しい保存方法はどれか」「医薬品の品質を保持するために適切なのはどれか」といった形で出題されます。
- 温度管理
- 光や湿度の影響
- 使用期限
選択肢では、「直射日光・高温・湿気を避ける」などの記述が正解になりやすいです。逆に「冷蔵庫で保管すればすべての医薬品が長持ちする」などの極端な記述は誤りなので注意しましょう。
![]()
9位:医薬品の販売時の情報提供(コミュニケーション)
登録販売者として最も重要な役割の一つが「購入者への適切な情報提供」です。試験では、販売時の説明や購入者とのコミュニケーションに関する問題がよく出題されます。
- 購入者の状態を把握する
- 他に服用中の薬があるか?
- 持病(高血圧・糖尿病・喘息など)があるか?
- アレルギーの既往歴はあるか?
- 適切な情報提供
- 用法・用量の説明(例:「食後30分以内に飲んでください」)
- 副作用や注意点の説明(例:「眠気が出る可能性があるので車の運転は控えてください」)
- 受診勧奨(例:「症状が3日以上続く場合は医師の診察を受けてください」)
「購入者が自己判断で誤った使用をしないよう、適切に説明する」ことが正解の選択肢になりやすいです。一方、「登録販売者は販売のみ行えばよい」などの記述は誤りです。
10位:一般用医薬品と医療用医薬品の違い
医薬品は、大きく「医療用医薬品」と「一般用医薬品(OTC)」に分かれます。試験では両者の違いや、一般用医薬品の分類(第一類・第二類・第三類)について問われることがあります。
- 医療用医薬品
- 医師の処方が必要
- 重篤な疾患の治療に用いられる
- 一般用医薬品(OTC)
- 処方箋なしで購入可能
- 軽度な症状の自己対処に使用
- 分類:
- 第一類医薬品 → リスクが高く、薬剤師の説明が必須(例:H2ブロッカー胃薬)
- 第二類医薬品 → リスクがやや高く、登録販売者が販売可能(例:解熱鎮痛薬)
- 第三類医薬品 → 比較的リスクが低い(例:ビタミン剤)
「第一類は薬剤師のみ販売可能」「第二類は登録販売者も販売できる」「OTCは軽度な症状の緩和に用いる」など、基本的な違いを覚えておけば正解を選べます。
まとめ
以上が、登録販売者試験・第1章の頻出問題ランキングTOP10です。特に1位~5位は毎年必ず出題されるので、しっかり理解しておきましょう。
試験対策として、過去問を解きながら、このランキングのポイントを意識すると効果的です。効率よく学習し、合格を目指しましょう!