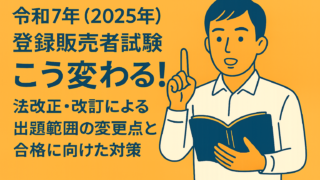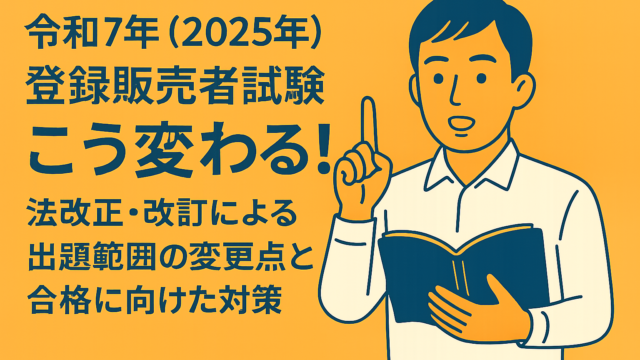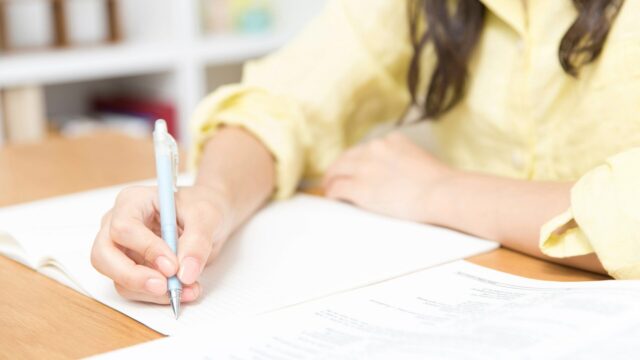登録販売者試験は、受験生にとって乗り越えなければならない壁となっています。この試験を突破するためには、ただ勉強するだけでは不十分。試験の内容を理解し、試験範囲に適応するための計画的なアプローチが必要です。16年の実務経験を持つプロフェッショナルが、4000問を超える過去問を分析し、登録販売者試験を解説します。
この記事では、試験の概要から具体的な学習、効率的な勉強法、さらには合格率と難易度に至るまで、あなたが試験に合格し、登録販売者としてのキャリアを築くために必要なことを網羅しています。読むことで、試験に向けた自信と合格までの道のりが分かります。
当サイトの管理人siroは、登録販売者として16年間の経験があり、店舗管理者・医薬品ECサイトを運営を行っています。2025年登販試験対策や登録販売者についてしっかりと解説します。
登録販売者試験とは?

登録販売者試験は、一般用医薬品(OTC医薬品とも呼ばれる)の販売に従事する人が受ける必要のある都道府県が実施する公的資格試験です。この試験の主な目的は、医薬品の販売に関する知識を持った人材を認定することにあります。医薬品は適切な使用が求められるため、消費者に正確な情報を提供し、安全な使用を促進する役割を登録販売者が担っています。
登録販売者試験の意義
近年、自己判断で医薬品を購入し使用する「セルフメディケーション」が推奨される中で、消費者が正しい選択を行えるようサポートすることの重要性が高まっています。OTC医薬品の適切な利用は、健康管理において重要であり、医療費の抑制にも貢献します。このような背景から、OTC医薬品の販売にあたっては、専門性を有することが求められ、登録販売者試験の合格が求められます。
試験の内容
登録販売者試験は、第1章から第5章に分かれ、医薬品の基礎知識、効能・効果や副作用、適正な使用方法、相談対応など、幅広い分野を問うものです。試験は筆記試験で120問実施され、約70%の回答を正解し、合格基準を満たした者のみが登録販売者とされます。合格するには、医薬品に関する理解とともに、消費者に対する適切なアドバイスができる能力が求められます。
- 第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」
- 第2章「人体の働きと医薬品」
- 第3章「主な医薬品とその作用」
- 第4章「薬事関係法規・制度」
- 第5章「医薬品の適正使用・安全対策」
各章を攻略するには
第1章
第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」を攻略するためには、医薬品の定義、種類、効果、副作用、安全使用のための基本知識が扱われます。効率的な学習のために最新のテキストを選び、重要な法規制や医薬品の分類を中心に学習を進めてください。法規制に関しては、医薬品医療機器等法に注目し、その基本的な枠組みを理解することが重要です。
第2章
「人体の働きと医薬品」を攻略するためには、人体の基本的な構造と機能、そしてそれに作用する医薬品の理解が必要です。まず、人体の主要な器官とその働きについて学習しましょう。これには心臓、肝臓、腎臓、消化器系などが含まれます。また、血液の循環や呼吸システム、神経システムの基本的な知識も欠かせません。
次に、医薬品が人体にどのように作用するかの基礎を把握することが重要です。これには、医薬品の吸収、分布、代謝、排泄の過程を理解することが含まれます。さらに、一般的に使用される医薬品の種類と、それらが治療を目的としてどのように体内で働くかを学びます。
第3章
「主な医薬品とその作用」を攻略するためには、まず、広範囲にわたる医薬品の種類と、それらがどのような作用を持つのかを理解する必要があります。具体的には、解熱鎮痛剤、風邪薬、胃腸薬、抗ヒスタミン薬など、日常的に使用される医薬品の特性と使われ方を学びます。
この章で重要なのは、各医薬品がどのような症状に効果があるのか、そして副作用や使用上の注意点をしっかり把握することです。例えば、解熱鎮痛剤がどのようなメカニズムで痛みを和らげるのか、風邪薬を選ぶ際のポイントは何か、などの具体的な知識が試験で問われます。
第4章
「薬事関係法規・制度」を攻略するには、医薬品に関連する法律や制度の理解が不可欠です。主に、医薬品医療機器等法(旧薬事法)、医薬品の分類(一般用医薬品、指定第二類医薬品など)、薬局やドラッグストアでの医薬品の取り扱いに関する規則、販売時の注意義務、広告規制に関する知識が求められます。
第5章
第5章「医薬品の適正使用・安全対策」を攻略するには、医薬品の正しい使用方法と安全な取り扱いに関する理解が必要です。この章では、医薬品の適切な保管方法、使用時の注意点、副作用の認識と対応、相互作用、過量摂取時の対処法などが主要なトピックとなります。
登録販売者の役割
登録販売者は、医薬品を販売する際に、消費者からの相談に応じ、症状や使用する医薬品に応じた最適なアドバイスを行います。また、医薬品の選び方や使用方法、保管方法など、正しい情報を提供することで、医薬品の安全な使用を支援します。消費者が自らの判断で適切な医薬品を選べるようにすることが、登録販売者には求められています。
![]()
試験の申し込み方法と日程

申し込み方法
- 試験情報の確認
まず、各都道府県の指定する試験実施機関の公式ウェブサイトまたは関連する公的機関の公告を通じて、試験の日程、申し込み期間、試験会場、受験料、申し込みに必要な書類などの詳細情報を確認します。 - 受験申請書の用意
登録販売者試験に申し込むためには、最初に受験申請書(または願書)を手に入れる必要があります。
この申請書の入手方法には、以下の選択肢があります。
・各都道府県庁など配布されている場所へ直接足を運び、受け取る。
・各都道府県庁に郵便で送ってもらうように依頼する。
・各都道府県庁のサイトからインターネットを通じてダウンロードする。 - 受験料の支払い
受験料の支払い方法は基本的に「収入証紙」を申請書に貼り付ける方法になります。 収入証紙とは税金を納付したことを証明する証紙です。 - 申し込み書類の準備
試験に申し込むには、申し込み書類を正確に準備する必要があります。これには、受験申請書、受験料の支払い証明書、写真などが含まれる場合があります。必要な書類は各区都道府県によって異なるため、事前に確認することが重要です。 - 受験申請書の提出
申請書の提出方法は郵送であり、提出先は受験者の所在地を管轄する各都道府県の試験管理機関となります。提出期限は都道府県ごとに設定されており、期限内に郵送することが必要ですので、各都道府県の指定する期限を確認し、その期日までに送付してください。不備がなければ後日に受験票が届きます。
試験日程の概要
登録販売者試験は年に各都道府県ごとに年1回実施され、試験日は都道府県によって異なります。一般的に、試験日程は数ヶ月前に公告され、申し込み期間もそれに伴って設定されます。試験日の数ヶ月前から準備を始めることが推奨されています。
(例①)令和5年の東京都
試験日:令和5年9月10日
申し込み期間:令和5年5月22日から6月2日
合格発表:令和5年10月20日
(例②)令和5年の富山県
試験日:令和5年9月6日
申し込み期間:令和5年6月5日から6月16日
合格発表:令和5年10月20日
案外、申し込み期間が短いためお忘れないようお申し込みください。
2025年 (令和7年度)登録販売者試験の日程と費用
※最終チェックは、各自治体の公式サイトや関連する情報源をご確認ください。
北海道・東北ブロック
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8月27日(水) | 6月3日(火)~6月24日(火) | 9月30日(火) | 18,200円 |
| 青森県 | 8月27日(水) | 6月18日(水)~6月24日(火) | 9月30日(火) | 17,600円 |
| 岩手県 | 8月27日(水) | 6月11日(水)~6月24日(火) | 9月30日(火) | 17,600円 |
| 宮城県 | 8月27日(水) | 6月11日(水)~6月24日(火) | 9月30日(火) | 17,600円 |
| 山形県 | 8月27日(水) | 6月11日(水)~6月24日(火) | 9月30日(火) | 17,600円 |
| 秋田県 | 8月27日(水) | 6月11日(水)~6月24日(火) | 9月30日(火) | 17,600円 |
| 福島県 | 8月27日(水) | 6月11日(水)~6月24日(火) | 9月30日(火) | 17,600円 |
関東・甲信越ブロック
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 8月28日(木) | 7月4日(金)~7月15日(火) | 10月3日(金) | 15,000円 |
| 茨城県 | 8月28日(木) | 6月18日(水)~7月1日(火) | 10月3日(金) | 15,000円 |
| 群馬県 | 8月28日(木) | 5月22日(木)~6月5日(木) | 10月3日(金) | 15,000円 |
| 山梨県 | 8月28日(木) | 6月16日(月)~6月27日(金) | 10月3日(金) | 14,000円 |
| 長野県 | 8月28日(木) | 5月19日(月)~5月30日(金) | 10月3日(金) | 15,300円 |
| 新潟県 | 8月28日(木) | 6月5日(木)~6月19日(木) | 10月3日(金) | 15,000円 |
首都圏ブロック
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 9月7日(日) | 5月19日(月)~5月30日(金) | 10月17日(金) | 13,600円 |
| 神奈川県 | 9月7日(日) | 5月19日(月)~5月30日(金) | 10月17日(金) | 14,300円 |
| 千葉県 | 9月7日(日) | 6月2日(月)~6月20日(金) | 10月17日(金) | 14,000円 |
| 埼玉県 | 9月7日(日) | 5月19日(月)~5月30日(金) | 10月17日(金) | 15,000円 |
北陸・東海ブロック
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 石川県 | 9月3日(水) | 6月3日(火)~6月17日(火) | 10月17日(金) | 15,000円 |
| 富山県 | 9月3日(水) | 6月3日(火)~6月17日(火) | 10月17日(金) | 15,000円 |
| 岐阜県 | 9月3日(水) | 5月16日(金)~6月13日(金) | 10月17日(金) | 15,000円 |
| 静岡県 | 9月3日(水) | 5月19日(月)~6月2日(月) | 10月17日(金) | 15,000円 |
| 三重県 | 9月3日(水) | 6月3日(火)~6月17日(火) | 10月17日(金) | 15,000円 |
| 愛知県 | 9月3日(水) | 6月3日(火)~6月17日(火) | 10月17日(金) | 15,000円 |
関西広域連合・福井・奈良ブロック
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 8月23日(土) | 6月2日(月)~6月16日(月) | 10月7日(火) | 12,800円 |
| 京都府 | 8月23日(土) | 6月2日(月)~6月16日(月) | 10月7日(火) | 12,800円 |
| 兵庫県 | 8月23日(土) | 6月2日(月)~6月16日(月) | 10月7日(火) | 12,800円 |
| 滋賀県 | 8月23日(土) | 6月2日(月)~6月16日(月) | 10月7日(火) | 12,800円 |
| 和歌山県 | 8月23日(土) | 6月2日(月)~6月16日(月) | 10月7日(火) | 12,800円 |
| 徳島県 | 8月23日(土) | 6月2日(月)~6月16日(月) | 10月7日(火) | 12,800円 |
| 奈良県 | 8月23日(土) | 6月2日(月)~6月16日(月) | 10月7日(火) | 13,000円 |
| 福井県 | 8月23日(土) | 6月2日(月)~6月16日(月) | 10月7日(火) | 13,000円 |
中国ブロック
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 10月21日(火) | 7月11日(金)~7月25日(金) | 11月28日(金) | 15,000円 |
| 岡山県 | 10月21日(火) | 7月11日(金)~7月25日(金) | 11月28日(金) | 15,700円 |
| 鳥取県 | 10月21日(火) | 7月11日(金)~7月25日(金) | 11月28日(金) | 14,300円 |
| 島根県 | 10月21日(火) | 7月11日(金)~7月25日(金) | 11月28日(金) | 14,000円 |
| 山口県 | 10月21日(火) | 7月11日(金)~7月25日(金) | 11月28日(金) | 14,740円 |
四国ブロック
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 香川県 | 10月21日(火) | 7月11日(金)~7月25日(金) | 11月28日(金) | 15,000円 |
| 愛媛県 | 10月21日(火) | 7月11日(金)~7月25日(金) | 11月28日(金) | 15,000円 |
| 高知県 | 10月21日(火) | 7月11日(金)~7月25日(金) | 11月28日(金) | 15,000円 |
九州・沖縄ブロック
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 12月21日(日) | 9月2日(火)~9月16日(火) | 令和8年1月下旬 | 13,000円 |
| 佐賀県 | 12月21日(日) | 9月2日(火)~9月16日(火) | 令和8年1月下旬 | 13,000円 |
| 長崎県 | 12月21日(日) | 9月2日(火)~9月16日(火) | 令和8年1月下旬 | 13,000円 |
| 大分県 | 12月21日(日) | 9月2日(火)~9月16日(火) | 令和8年1月下旬 | 13,000円 |
| 熊本県 | 12月21日(日) | 9月2日(火)~9月16日(火) | 令和8年1月下旬 | 13,000円 |
| 宮崎県 | 12月21日(日) | 9月2日(火)~9月16日(火) | 令和8年1月下旬 | 13,000円 |
| 鹿児島県 | 12月21日(日) | 9月2日(火)~9月16日(火) | 令和8年1月下旬 | 13,000円 |
| 沖縄県 | 12月21日(日) | 9月2日(火)~9月16日(火) | 令和8年1月下旬 | 13,000円 |
※今後、各自治体から最新情報が公開される可能性がありますので、受験を検討されている方は、必ず各都道府県の公式ウェブサイトや薬務課等にて最新情報をご確認ください。
※受験料や試験日程は変更される可能性があります。願書受付開始前には必ず公式情報をチェックされることをおすすめします。
学習教材と効率的な勉強法

学習教材
テキスト
まず、最新のテキストを用意しましょう。テキスト選びは合格への第一歩です。自分に合ったテキストを選ぶために、以下のポイントを参考にしましょう。
- 内容が最新版であること
法改正や薬の成分変更など、試験内容は常に更新されています。最新版のテキストを選ぶことで、最新の情報を効率的に学習できます。 - 読みやすく、わかりやすい解説があること
専門用語が多く、内容が理解しにくいと感じたら、別のテキストを試してみましょう。イラストや図表を効果的に活用しているテキストもおすすめです。 - 自分に合ったレベルのテキストを選ぶこと
初心者向けのテキストから、より掘り下げた内容のテキストまで、さまざまなレベルのテキストが販売されています。自分の知識レベルに合ったテキストを選ぶことで、効率的に学習を進められます。
過去問
過去問は、試験問題の傾向を把握し、実力を確認するのに最適な教材です。過去5年間の試験1回分、120問を最低5回(120×5=600問)は解き、間違えた問題は解説を読み込み、理解を深めましょう。
その他の教材
- 問題集
過去問に加えて、より多くの問題を解きたい場合は問題集を活用しましょう。 - 模擬試験
本番の試験形式を体験することで、時間配分や解答テクニックを身につけることができます。 - 映像
通勤時間やスキマ時間に学習したい場合は、映像教材がおすすめです。(オンライン通信講座、YouTubeなど)
効率的な勉強法
1. 学習計画の立案
- 目標設定
試験日までの時間を把握し、学習計画を立てます。具体的な目標を設定し、毎日の勉強時間も決めておきましょう。 - 優先順位の決定
試験範囲全体を把握し、自分の苦手な領域を特定します。苦手分野を重点的に勉強することで、効率的に知識を広げていきましょう。
2. 基礎知識の確固たる理解
- 基本テキスト
最新の登録販売者試験のテキストを選び、基礎知識をしっかりと身につけます。わかりやすい解説があるテキストを選ぶと良いでしょう。 - 法規問題への対応
医薬品販売に関わる法律や規制についての理解も深めます。普段使わない言い回しや、法律用語などに対する対応も必要です。
3. 過去問題の解析
- 過去問の活用
過去問を解くことで、試験の形式や出題傾向を把握します。間違えた問題については、解説を読み解き、理解を深めることが重要です。
4. 効率的なインプットとアウトプット
- インプット
新しい情報をテキストや講義で学びます。この際、アクティブラーニング(主体的な学習)の手法を取り入れると良いでしょう。例えば、読んだ内容を自分の言葉で説明するなどが効果的です。 - アウトプット
学んだ知識を使って問題を解く、または人に説明することで、理解を深めます。過去問や模擬試験を利用して、実際に試験のような形式で問題を解いてみましょう。
5. 模擬試験の実施
- 本番さながらの練習
模擬試験を実施することで、時間配分や試験におけるプレッシャーに慣れることができます。また、自身の実力を客観的に把握することができます。
7. モチベーションの維持
- 目標の設定
長期間の勉強になるため、途中で挫折しないよう小さな目標を設定し、達成するたびに自分を褒めるなどしてモチベーションを維持します。また、目標を明確する、勉強仲間を見つける、ご褒美を設定するなど、自分に合ったモチベーション維持方法を見つけましょう。
8.暗記のコツをつかむ
- 分割して学習する(チャンキング)
- 大量の情報を一度に暗記しようとすると、なかなか記憶に残りません。情報を小さな単位(チャンク)に分割し、少しずつ記憶していく方法です。たとえば、電話番号を覚える際に3桁ずつに分けるのと同じ原理です。
- 繰り返し復習する(スペースド・リピティション)
- 一度覚えたことをそのままにしておくと忘れてしまうので、繰り返し復習することが重要です。ただし、復習の間隔を徐々に長くしていく「スペースド・リピティション」という方法が効果的です。これにより、長期記憶に移行しやすくなります。
- イメージやストーリーを使う(ビジュアル化)
- 情報を視覚的なイメージやストーリーに結びつけることで、記憶に残りやすくなります。例えば、単語を覚える際にその単語から連想されるイメージを思い浮かべると良いでしょう。
- 筆記する
- 書き留めることで記憶の定着を促します。特に手書きでノートにまとめると、脳がより積極的に情報を処理し、記憶に残りやすくなると言われています。
- 語呂合わせを利用する
- 情報を音楽やリズム、語呂合わせにすることで、覚えやすくなります。特に、日付や一覧などの順序を覚える際に有効です。
- 健康な生活を心掛ける
- 十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事は記憶力に良い影響を与えます。脳の健康を維持することが、効果的な暗記には欠かせません。
合格率と難易度
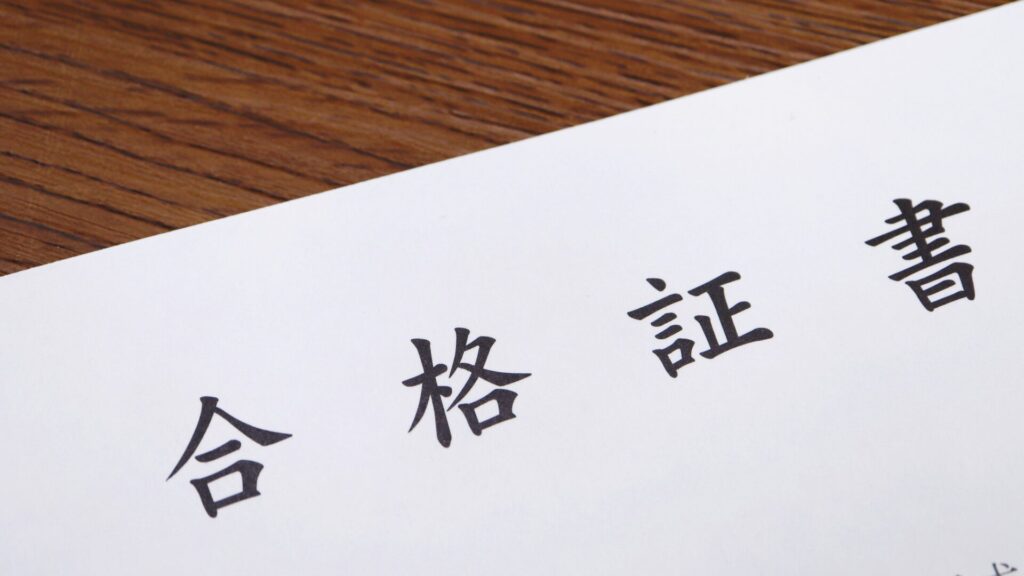
合格率の推移
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2019年度 | 6万5288人 | 2万8328人 | 43.40% |
| 2020年度 | 5万2959人 | 2万1953人 | 41.50% |
| 2021年度 | 6万1070人 | 3万82人 | 49.3% |
| 2022年度 | 5万5606人 | 2万4707人 | 44.4% |
| 2023年度 | 5万2214人 | 2万2814人 | 43.7% |
| 2024年度 | 5万4526人 | 2万5459人 | 46.7% |
しかし、2021年度には受験者数が6万1070人に増加し、合格者数も3万82人に上がり、合格率は49.3%と大幅に改善しました。
2024年度の試験は、一部の地域では台風の影響により試験日が延期されるなどの対応がありました。全体的に合格率は前年より上昇し、北海道や東海地方で高い合格率が見られました。一方、九州や沖縄地方では合格率が低めとなっています。
試験の難易度
データから読み取れるのは、登録販売者試験が一定の難易度を保っているという事実です。合格率が年によって若干の変動はあるものの、おおむね40%台を保っています。これは、試験が広範囲にわたる知識を問うものであり、単に暗記するだけではなく、実践的な理解が求められるためです。医薬品の基本知識、人体のはたらき、医薬品の成分や副作用など、専門的な内容を深く理解し、顧客に対する適切なアドバイスができる能力が試されます。
よくある質問 (FAQ)
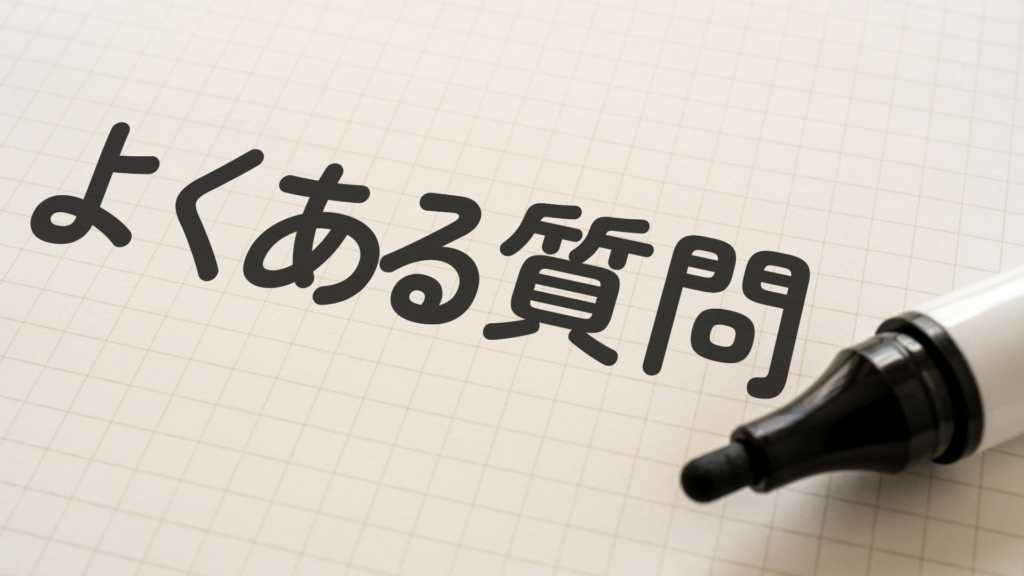
- 登録販売者試験の受験資格はありますか?
登録販売者試験を受験するために特別な資格は必要ありません。 - 登録販売者試験の合格後、資格の有効期限はありますか?
登録販売者としての資格に有効期限は設けられていません。一度合格し登録を行えば、資格は生涯有効です。ただし、登録更新に際しては、一定の研修を受講する必要がある場合があります。 - 登録販売者試験の受験料はいくらですか?
受験料は都道府県や試験の実施機関によって異なります。12,800~18,200円の範囲で設定されていますが、正確な金額については各都道府県の公式ウェブサイトで確認してください。 - 試験合格後の手続きはどうすればよいですか?
試験合格後、登録販売者として登録するための手続きが必要です。手続きには、合格通知書の提出や登録料の支払いなどが含まれる場合があります。具体的な手続きの流れについては、合格通知に同封されている指示に従い行いましょう。 - 登録販売者試験に不合格だった場合、再受験は可能ですか?
不合格の場合でも、再受験は可能です。受験資格に制限はないため、次回の試験に向けて再度申し込むことができます。ただし、再受験の際には新たに受験料を支払う必要があります。 - 登録販売者として働くには、どのような場所がありますか?
登録販売者は、ドラッグストア、薬局、スーパーマーケットの医薬品コーナー、ホームセンターなど、一般用医薬品を取り扱うさまざまな場所で働くことができます。また、医薬品の知識を活かしたコンサルタントや講師としての活動も可能です。 - 登録販売者試験の勉強にかかる期間はどのくらいですか?
勉強にかかる期間は、個人の基礎知識や学習の進め方によって大きく異なります。一般的には、3ヶ月から半年程度の準備期間を設ける受験者が多いですが、試験範囲の広さや難易度を考慮し、個々の状況に合わせて計画を立てることが重要です。

まとめ
登録販売者試験は、ただ単に多くの情報を覚えるだけではなく、試験の本質を理解し、挑むことが重要です。この試験は、一般用医薬品(OTC医薬品)の適切な販売を担うプロを育成することを目的としており、受験生は医薬品の基礎知識から、効能・副作用、正しい使用方法に至るまで、幅広い知識が求められます。また、消費者への適切なアドバイスを提供できる能力も対象となります。
合格ラインは、試験全体で70%を超えることです。しかしながら、各章ごとに最低限必要な得点率が設定されており、この最低ラインは35%〜40%です。したがって、自分の不得意な部分をしっかりと理解し、それらの分野を強化する努力が、試験に合格するためのカギとなります。
最後に、登録販売者として活躍するためには、試験合格後も継続的な学習が不可欠です。医薬品に関する知識は日々更新されるため、最新の情報を常にチェックし、消費者への正確な情報提供を心掛けることが重要です。試験合格は、登録販売者としての第一歩に過ぎず、その後のキャリアを通じて、社会に貢献を果たすことが期待されています。
合格への近道「通信講座」三幸医療カレッジ合格率89%
合格には、医薬品の特性、人体の働き、法規制など、幅広い知識が求められます。ただし、資格取得のプロセスは容易ではありません。推奨される学習時間は250〜300時間にも及び、試験の範囲も広範囲にわたります。これを乗り越えるには、効率的で計画的な学習方法が必要不可欠です。
ここで三幸カレッジの通信教育をご紹介します。三幸カレッジは、登録販売者資格取得を目指す方々に特化したカリキュラムを提供し、全国平均の2倍の合格率があります。自宅での学習を中心に、効率的かつ実践的な指導を行うことで、試験合格へと導きます。三幸カレッジでは、豊富な教材と経験豊かな講師陣によるサポートがあり、学習者一人ひとりのニーズに応じた学習計画を立てることができます。