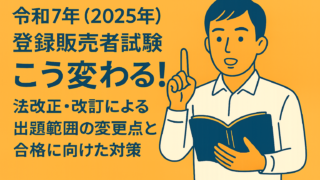薬事の現場には多くの専門職が存在しますが、代表的なのが「登録販売者」「薬剤師」「調剤薬局事務」という三大キャリアです。これらの職種は、日本の医療や健康支援の最前線で活躍しており、その業務内容はさまざまです。
本記事では、15年以上の実務経験を持つベテランが、これらの三職種の内容、資格取得の過程、そしてキャリア形成について詳しく解説します。
これらの情報が転職や新たなキャリア形成の参考になるだけでなく、薬事業界での長期的なキャリアプランを考える上での指針となることを目指しています。それぞれの職種が具体的に何をやり、どのようにして薬事のプロとして高めていけるのか?そのポイントを押さえていきましょう。
当サイトの管理人siroは、登録販売者として16年間の経験があり、店舗管理者・医薬品ECサイトを運営を行っています。2025年登販試験対策や登録販売者についてしっかりと解説します。
登録販売者について

登録販売者とは
登録販売者は、一般用医薬品の販売を行うことができる資格を持った専門家です。具体的には、風邪薬や鎮痛剤など、処方箋が不要な「第二類医薬品」と「第三類医薬品」の販売が可能です。この資格は2009年に薬事法が改正されたことにより設けられ、薬剤師が不在の店舗でも一定の医薬品を取り扱うことが認められています。
資格の取得方法
登録販売者の資格を取得するには、年に1度実施される試験に合格する必要があります。試験は医薬品の基礎知識、薬機法や適正使用の知識を問う内容などあり、試験の合格後に都道府県に登録を申請することで資格が認められます。試験の内容は広範にわたるため、合格には相応の勉強が必要ですが、特定の学歴や前職の経験は問われません。
- 勉強: 登録販売者になるための専門知識を身につける必要があります。医薬品の基礎知識から法規まで、幅広い学習が求められます。
- 試験: 各都道府県が実施する登録販売者試験に合格する必要があります。
- 登録: 試験合格後、所定の手続きを経て、登録販売者として登録されます。
キャリアの例
登録販売者としてのキャリアはさまざまです。ドラッグストアや薬局、スーパーマーケットの薬売り場などでの勤務が一般的ですが、これらの場所での顧客対応や商品管理、在庫管理レジ打ちなどが業務となります。また、経験を積むことで店舗管理やマネジメントのポジションを目指すことも可能ですし、独立して自身の店舗を持つこともできます。資格を生かした教育や研修の講師を務めることも、キャリアの一つとして考えられます。
登録販売者は、医薬品の知識を活かしながら、地域社会の健康を支える役割を担っています。将来的には、より専門性を高めたり、さらなる資格を取得することで、そのキャリアを広げていくことも可能です。

薬剤師について

薬剤師の種類
薬局薬剤師
処方せんによる調剤、薬の正しい使い方の指導、薬の飲み合わせのチェックなどを行っています。また、一般用医薬品を販売する際には、消費者の求めに応じて、その症状に合ったくすりを探したり、症状の度合いによっては専門医等への受診を勧めたりするなど、セルフメディケーション(軽度な身体の不調は自分で手当てする)のサポートをします。
さらに、漢方薬や健康食品・サプリメントの選び方、在宅介護の支援、禁煙サポート、ドーピング可否に係る相談など、専門知識で対応をしている薬局薬剤師もいます。
病院・診療所の薬剤師
薬の調剤、注射薬や点滴の調製・管理、適切な薬の飲み方の指導、臨床検査などを行うほか、くすりの在庫管理・品質管理を行います。
薬を有効かつ安全に使用するために、血液中の薬の濃度を測定し、患者さん個々に適した投与量や投与方法を決定する、薬物治療モニタリングや、薬の吸収や副作用による食欲不振を把握し、その改善策を医師等に助言し、栄養剤について患者・家族に説明・指導する、栄養サポートチームとしての役割も担っています。
製薬会社の薬剤師
薬の研究・開発や品質管理のほか、薬に関する情報を収集・管理し、医師、薬剤師(病院や薬局)、看護師等からの問い合わせに応じて、適切に情報を提供しています。
また、化粧品は薬事法で取り扱いを規制されていることから、化粧品メーカーで、化粧品の商品開発などを行う薬剤師もいます。
卸売販売会社の薬剤師
病院や薬局への薬を売る、薬の問屋に勤める薬剤師です。薬の保管管理を行い、病院や薬局からの薬の問い合わせに対応して情報を提供しています。
行政の薬剤師
国、県庁、保健所などに勤める薬剤師です。薬事監視員として、医薬品等の表示・保管・適正使用について調査、指導、監視をしたり、公立研究機関では、試験検査、医薬品研究などを行っています。
災害時の薬剤師
突然発生する大規模災害時に、救護所・避難所等で医療活動へ積極的に参加し、使用薬剤に関する助言・服薬指導を行うことで、薬剤師としての能力を発揮して救護活動に取り組みます。
学校の薬剤師
薬局薬剤師や病院・診療所の薬剤師が教育委員会等から委任されて、小中学校並びに高等学校において、学校医や学校歯科医とともに、学校保健の仕事をします。
また、児童生徒などを対象に、くすりの正しい使い方や薬物乱用防止、たばこの害、アルコールの害などの授業を行うこともあります。
資格の取得方法
- 薬学部のある大学に入学
薬剤師になるためには、まず6年制の薬学部に入学する必要があります。ここで、基本的な医薬知識や薬学に関連する広範な教育を受けます。 - 薬学共用試験に合格
大学在学中に、薬学共用試験に合格する必要があります。これにより、実務実習の資格を得ることができます。 - 病院や薬局での実務実習
薬学部の学生は、6年次に病院や薬局での実務実習を行います。この実習は、現場での具体的な業務経験を積むために不可欠です。 - 薬剤師養成課程を修了
6年間の学習を経て、薬学部を卒業します。この時点で、薬剤師国家試験の受験資格を得ることができます。 - 薬剤師国家試験に合格
薬学部卒業後、薬剤師国家試験に挑戦し、合格する必要があります。試験は年1回で実施されます。 - 薬剤師名簿に登録
国家試験に合格した後、厚生労働省が定める薬剤師名簿に登録することで、正式に薬剤師として認められます。
以上のステップを経て、薬剤師としての資格を得ることができます。薬剤師は医療の現場で必要とされ、患者の健康を支えるための責任ある仕事を担います。このプロセスを経て、病院、薬局、製薬会社などで活躍する道が開けます。
調剤薬局事務について

調剤薬局事務の業務
調剤薬局事務の業務内容には、受付、会計、請求業務の3つの部分が含まれます。それぞれの業務について詳しく解説します。
- 受付業務
調剤薬局での受付は、患者さんが持参する処方箋、保険証、お薬手帳を受け取ることから始まります。これらの書類に記載されている情報を確認し、必要に応じて新規患者のデータをシステムに登録します。また、受付時には処方箋の有効期限や保険証の情報を慎重にチェックし、問題がないことを確認後、これらを薬剤師に渡すことも受付業務です。 - 会計業務
患者から薬代を受け取り、会計処理を行うのがこの業務の内容です。会計業務では、パソコンを使用して薬代の計算を行いますが、金銭を扱うため正確さが求められます。会計が終わると、適切な領収書の発行を行います。 - 請求業務
保険診療における患者の医療費の保険分を保険者に請求する業務です。これは「レセプト業務」とも呼ばれ、薬剤師や専用ソフトウェアによって作成された調剤報酬明細書(レセプト)に基づき行います。この業務には、保険請求に関する知識が必要であり、データ管理と処理能力が求められます。
これらの業務の他にも、調剤薬局事務では医薬品の在庫管理や発注、薬剤師のサポート作業、店内の整理整頓など、補助的な業務が含まれます。調剤薬局事務は、無資格・未経験から始めることが可能であり、転職や復職にも強い職種です。
必要なスキルと資格
調剤薬局事務には特定の資格は必要ありませんが、知識を有することが望ましいため、多くの場合、調剤薬局事務に関連する民間資格を取得することが推奨されます。
調剤薬局事務関連資格
- 調剤事務管理士
調剤薬局で必要とされる知識全般をカバーし、業務の効率化を支援するスキルが学べます。 - 調剤事務実務士
薬剤師のサポートを行う上で必要な専門的な知識と技術を認定する資格です。 - 調剤薬局事務検定試験
具体的な業務に必要な基礎知識と応用知識を問う試験です。 - 調剤事務認定実務者
実務に必要な法規と薬剤知識を問う資格で、実技試験も含まれるため実務能力の高さを証明できます。 - 調剤報酬請求事務専門士
調剤報酬の計算と請求業務に関する専門性を認定する資格で、業務の精度を向上させます。 - 医療保険調剤報酬事務士
医療保険を利用した調剤請求業務全般にわたる知識と技術を認定します。
これらの資格を持っていると、調剤薬局での採用が有利になり、専門性をアピールすることができます。また、医療機関特有の用語やプロセスを理解していること、正確なデータ入力スキル、高いコミュニケーション能力が求められます。
資格取得の勉強方法
資格取得を目指す場合、独学または通信・通学講座を利用する方法があります。独学は時間とコストを自由に管理できる一方、通信講座や通学講座では専門的な指導を受けることができ、効率よく学べるメリットがあります。どの方法を選択するかは、個人のライフスタイルや学習スタイルによりますが、未経験者や基礎知識が不足している場合は、講座を受けることをおすすめします。
調剤薬局事務に向いている人
1. コミュニティケーションができる人
調剤薬局事務は患者さんと直接対話する機会が多いため、コミュニケーション能力が重要です。親しみやすい態度で接することができる人は、患者さんからの信頼を得ながら業務を進めることができます。
2. チームワークを大切にできる人
薬局内では薬剤師や登録販売者などと協力して業務を行うため、チームワークが必要です。互いに情報を共有し、助け合うことで、高付加価値なサービス提供が可能になります。
3. 細かい作業が苦にならない人
調剤薬局事務の業務は、処方せんの入力や保険請求など、細部にわたる注意が必要です。細かい数字の扱いや文書の管理に慎重で、ミスを減らすことができる几帳面な人材が求められます。
4. タッチタイピングで作業ができる人
業務の多くはコンピュータを使用して行われるため、パソコン操作スキル(入力作業やオフィスソフトの使用)が必要です。これらのタッチタイピングの技術があると、仕事の効率が向上します。
5. 数字にアレルギーがない人
保険請求や薬の在庫管理など、数字を扱うことが頻繁にあります。計算が得意で、数値に関するエラーを減らせる能力がある人には、調剤薬局事務が向いています。
これらの特徴を持つ人は、調剤薬局事務として馴染む可能性が高いです。もしこのような特性やスキルがある場合、調剤薬局事務の職を積極的に目指すと良いと思います。
協力関係における相乗効果

三職種の協力関係
薬事の現場で活躍する「登録販売者」「薬剤師」「調剤薬局事務」という三職種は、それぞれ独自の役割を持ちつつも、互いに密接に協力し合っています。お互いが薬事の現場における効率的かつ効果的な薬に関わる業務を可能にしています。
- 登録販売者と薬剤師の協働
登録販売者は、薬剤師が不在の時にも一般用医薬品の販売を担うことができ、薬剤師と共に薬に関する広範なニーズに対応します。薬剤師は、より専門的な医薬品の処方と管理を行い、登録販売者はそれを補助し、顧客への基本的な薬事指導を提供します。 - 薬剤師と調剤薬局事務の連携
薬剤師が安心して調剤業務に専念できるよう、調剤薬局事務はレセプト作成や患者データの管理、保険処理などの事務作業を担います。この効率的な業務分担により、薬剤師は薬の調合と患者や顧客の対応により多くの時間を割くことができます。 - 登録販売者と調剤薬局事務の相互サポート
登録販売者と調剤薬局事務の間では、特に薬剤師が不足している地域や時間帯において、一般用医薬品の販売や顧客対応で協力し合います。この協力により、薬局運営のスムーズな流れが保たれ、患者や顧客へサービスの質が向上します。
相乗効果
これらの職種間で協力することにより、医薬品の供給から患者や顧客への教育まで、医療サービスの各段階において相乗効果が生まれます。
- 効率の向上
各職種が専門性を活かし、タスクを分担することで、全体の業務効率が向上します。 - リスクの軽減
薬の誤処方や管理ミスのリスクを減らすために、薬剤師と調剤薬局事務が連携して情報を共有し、チェック体制を強化します。 - 患者や顧客の満足度の向上
登録販売者と薬剤師が協力して患者や顧客に対する薬事指導を行うことで、より理解を深め、満足度を高めることができます。
これらの相乗効果は、薬事の現場におけるチームワークが重要で、それぞれの職種が互いに協力し合うことで、より高品質な医療サービスの提供が可能になります。
まとめ
本記事では、日本の薬事の現場における三職種である「登録販売者」「薬剤師」「調剤薬局事務」について、その業務内容や資格取得の過程について詳しく解説しました。各職種がどのような役割をし、どのような道を歩むかを具体的に紹介しました。
登録販売者は、一般用医薬品の販売を行う専門家として、地域社会の健康支援に貢献しています。資格取得には年に一度の試験に合格し、都道府県に登録する必要があります。就職先は、ドラッグストアや薬局での勤務から、店舗管理や独立、教育者としての役割まで広がっています。
薬剤師は、処方せんの調剤、薬の正しい使用方法の指導、薬の飲み合わせチェックなどを行います。資格を取るには薬学部での6年間の学習と国家試験の合格が必要で、その後、病院、薬局、製薬会社などで活躍の場を見つけることができます。
調剤薬局事務は、医療現場のバックオフィスを支える業務です。具体的には、受付、会計、保険請求などの業務を担当し、調剤薬局の運営をスムーズにします。この職種は無資格・未経験から始めることができ、民間資格を取得することで専門性を高めることが推奨されています。
これらの職種は、互いに密接に協力しながら、患者さんや顧客に対するサービスの質を高め、業務効率を向上させています。薬剤師と調剤薬局事務の連携は、薬の誤処方リスクの軽減や情報共有の強化に寄与しており、チームワークの重要性が強調されます。
このように、登録販売者、薬剤師、調剤薬局事務の三職種は、それぞれが独自の専門知識とスキルを活かしながら、日本の医療と健康支援の現場で頑張っています。
合格への近道「通信講座」三幸医療カレッジ合格率89%
合格には、医薬品の特性、人体の働き、法規制など、幅広い知識が求められます。ただし、資格取得のプロセスは容易ではありません。推奨される学習時間は250〜300時間にも及び、試験の範囲も広範囲にわたります。これを乗り越えるには、効率的で計画的な学習方法が必要不可欠です。
ここで三幸カレッジの通信教育をご紹介します。三幸カレッジは、登録販売者資格取得を目指す方々に特化したカリキュラムを提供し、全国平均の2倍の合格率があります。自宅での学習を中心に、効率的かつ実践的な指導を行うことで、試験合格へと導きます。三幸カレッジでは、豊富な教材と経験豊かな講師陣によるサポートがあり、学習者一人ひとりのニーズに応じた学習計画を立てることができます。